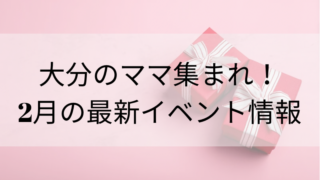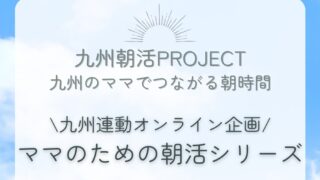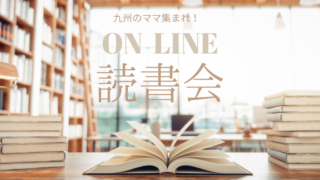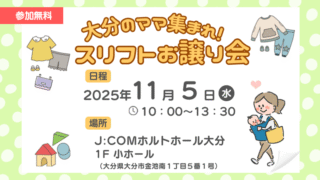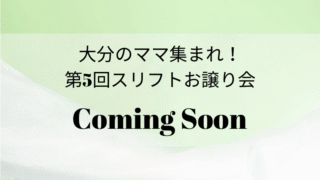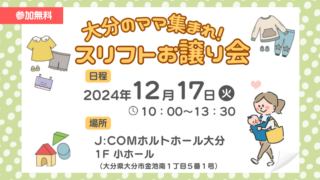「あのとき近所に頼れる女性がいたら……」
県外出身の私が大分県に移住して妊娠、出産。
周囲に頼れる人がいない中での子育ては「孤育て」といわれるほど孤独や不安が募ります。
特に心細かったのが夫の出張中に台風が接近したとき。一人で生後10ヶ月と2歳の幼い子どもを抱えた私は孤立無援の恐怖を覚えました。
そのとき痛感したのが「地域のつながり」の大切さ。
近所の誰かに助けを求め、相談できる関係があればどんなに心強かったことか。核家族化が進んで地域のつながりが希薄になった今、慣れない土地で子育て中のママは、非常時の支援者探しに苦労したことがあるのではないでしょうか。
大分県が推進する「女性の地域活動実戦力向上支援事業」は、そのような災害時や子育てなど、多様化する地域の課題や変化に対応できる実践力の向上と、地域活動の活性化につながる女性の取り組みを支援する事業です。
この事業の一環として、「ママや女性の孤独の防止」をミッションに掲げてママ集まれ!を運営する合同会社co-e connect が今年度のモデル事業を受託。地域活動が盛んな日出町豊岡地区の婦人会の皆さんと子育て中のママ世代の交流・連携を目指して、全3回にわたる研修会を行いました。
世代と世代をつなぎ、お互いを理解するための段階的アプローチ
「婦人会」とは、生涯学習や健康福祉、社会奉仕など、地域に根ざした活動をする女性団体で構成員は主に60〜70代。長年にわたる地域活動を通じて、さまざまなノウハウやネットワークを持つ女性の集まりですが、核家族や共働き世帯が増え、婦人会世代と子育て世代が接する機会は激減しています。
そこで、交流の前ステップとして、お互いを理解し合うためのコミュニケーション講座を実施。
第1回は婦人会向け、第2回はママ向け、そして第3回の講座では婦人会の皆さんとママたちが合同で参加して、「防災」をテーマとした世代間交流を行いました。
まずは相手を理解することから。「多文化共生」を考える婦人会研修会
第1回は、2024年10月29日(火)に開催された豊岡地区婦人会研修会。
まずは多文化共生マネージャーの森川寿子さんが「多文化共生時代のまちづくりとコミュニケーション」をテーマにお話しされました。

紐だけ、絵だけで物事を伝えるワークショップでは、言葉を使えないもどかしさや正しく伝わったのかわからない不安など、伝えることの難しさを体感しました。
続いて、大分のママ集まれ!前副代表・九州のママ集まれ!副代表 森田から、住む場所に関心がなくても生きていける今、どうすれば地域活動を活性化できるのか?価値観の違いを認め、他人を尊重する考え方についての講演。国や文化、年齢を問わず、同じ地域に住む人たちが円滑に暮らすために必要な意識やコミュニケーションのあり方について学ぶ機会になりました。

【参加者感想】
川野さん「勤務先はAPUの留学生アルバイトも多く、日本語特有のあいまいな表現を使わず、わかりやすい言葉を心がけていたので、多文化共生の話にとても共感しました」
安部さん「森田さんのお話を聞いて、もう少し私たちの方から若い世代に声をかけて、コミュニケーションがとれる場をもちたいと思いました。こちらから声がけして行動したいなと考えております」
つながりが生む新しい子育ての形。世代間ギャップを埋めるママ向け研修会
第2回は、2024年12月20日(金)に開催された子育てママ向け研修会。
第1回と同じく、今度はママ世代に向けた森川寿子さんの多文化共生のお話です。
紐と絵とワークショップでは、婦人会の感想と同じように多くのママがもどかしさや不安を抱く中、「言葉がなくても意外と伝わるものだと感じました」と捉えた参加者も。

障がいなどで言葉が使えない場合は、表情や仕草から相手の意思を読み取る観察力や想像力が必要になります。同じ日本人同士でも、地域における多様性や多文化の「共生」には、言葉に頼らないコミュニケーションも大事だと気づき、視野が広がりました。
続いて、森田による世代間交流の講演。
事前アンケートでは、約半数が世代間交流について「わからない」「面倒」「負担感を感じる」という回答でしたが、研修後には7割を超えるママの意識が「交流したい」に変化。

世代間交流に対するイメージが変わるきっかけになったようです。
【参加者感想】
ゆうみさん「地域全体で子どもを育てたいが、きっかけがつかめずにいることに気づきました」
こずえさん「いつ災害が起こるかわからないので、普段から交流があった方が安心だと思いました」
ちひろさん「SNSがなかった世代は対面での会話が情報共有の手段だったことが理解できたので、相手の伝えようとしてくれる思いを受け取れる人になろうと思いました」
「防災」を通じた世代間交流。“ 顔の見える関係 “が心強い味方に
第3回は、2025年1月21日(火)に開催。
事前研修を受けた婦人会の皆さんと子育て中のママとの合同研修会です。
アイスブレイクを交えた自己紹介で緊張がほぐれた後は、婦人会から災害時に簡単に作れる防災食の紹介。計量カップを使わずにお米を炊く方法など、先輩ママの経験に基づいたノウハウはインターネットが使えない環境でも役立ちます。


続いて、大分DMAT隊員で東日本大震災の際は大分赤十字救護員として被災地で活動した新副代表 田中舞による防災講座。
ストッキングなどの日用品を使った応急手当を実践してみたり、三人の子どもを育てるママとして田中が実際に備えている避難バッグを背負ってみたり、グループワークを通じた情報共有が活発に行われました。


婦人会の皆さんもママ世代も、家庭に足腰が不自由な高齢者や乳幼児、いわゆる「災害弱者」を抱えることが多い立場。日頃から信頼関係を作っておくことが、いざというとき自分と家族を守る最大の防災になると感じました。

世代を超えた女性同士のつながりは、一人では知り得なかった知識やノウハウ、何よりも安心感を与えてくれます。それはどの世代にとっても孤独や不安を減らし、非常時は心強い力になるはず。いろんな世代が集まりやすい場が増え、子育てを多世代で楽しめる地域づくりが、子どもにとっても自分にとっても明るく豊かな未来につながると感じた3日間でした。
写真・文:山口紗佳