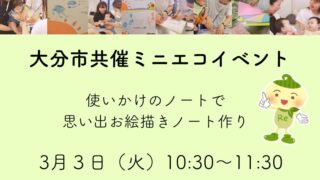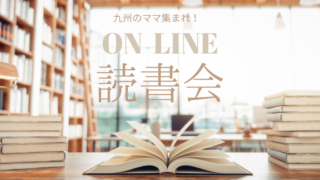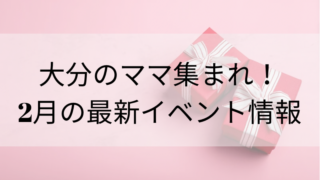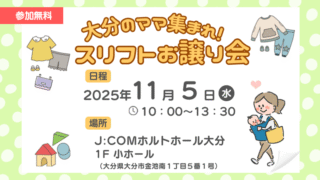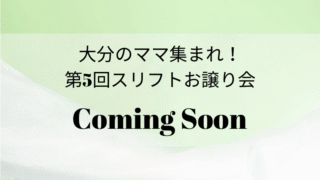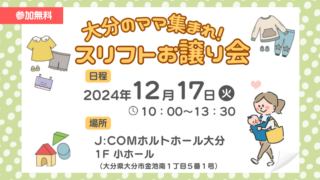こんにちは!森田典子(ママ集まれ!副代表/思春期の親子関係専門家)です。
お子さんのスマホやゲーム、YouTubeとの付き合い方に、頭を悩ませていませんか?
「スマホ、いつから持たせるべき?」
「ゲームばっかりで心配…」。
同じように悩んだり、不安になったりしているママは少なくないはず!
今の子どもたちの目の前には、生まれた時からスマホやタブレット、様々なデジタル機器が存在しています。彼らはまさに、デジタル機器と共に育つ世代。
だからこそ、デジタル機器を『使われる側』ではなく『使いこなす側』になることが、これからの人生を豊かにする上でとても大切になります。
それには、「今どんな風に使っているか」それが彼らの未来を大きく左右します。
今回は、皆さんのお悩みに寄り添いながら、明日から実践できるヒントをお伝えしたいと思います。

スマホ漬けに潜む「3つの落とし穴」
なぜ、あんなにスマホに夢中になるんだろう。と首を傾げることありませんか。
夢中になることで起きる問題は、次の3つが考えられます。
- 画面の向こうの見えないトラブル: 親の知らないところで、友達との誤解やいじめなど、デジタルの世界ならではのトラブルが起こりやすくなります。
- 思春期の脳はスマホに弱い?!: 実は、思春期の子どもの脳はまだ未熟。特に感情のコントロールや判断を司る「前頭前野」が発達途中なので、スマホやゲームの刺激に「夢中になりやすい」傾向があるんです。
- リアルな体験の不足: 友達と顔を合わせて遊んだり、失敗から学んだりといった、本来なら経験すべき大切な成長の機会が、スマホに費やす時間によって奪われてしまうことがあります。例えば、相手の表情が見えないやり取りでは、感情の機微を読み取る機会が減ってしまいます。
さらに、夢中になりすぎることで、体調不良、睡眠不足、集中力の低下などの問題も起きてきます。
と、ここまで聞くと、「スマホは悪」「デジタル機器は悪」と感じる方もいるかもしれません。しかし、学校でもタブレットが学習に取り入れられているように、決して「悪」というわけではないんです。
悪にさせず、効果的に使うためにも、これからの子ども達は「使われる側」ではなく、「使う側」になることが大切なんです。
それには、特に小学生以降で重要になるのは、親子でどう向き合い、どうルールを作っていくかが大切になります。
みなさんは、ルールをどんな風に作って、どう活用していますか?
これこそが、最大の鍵になります。
だって、Wi-Fiやスクリーンタイムを制限するだけではうまくいかないですよね。

私の経験から伝えたい「3つの大切なこと」
実は、私も息子が一時的に軽いスマホ依存傾向になった経験があります。
その時痛感したのは、
- 子どもの些細な変化に気づける親でいること。
- 話し合いができる風通しの良い親子関係を築くこと。
- 子ども自身がルールの大切さを理解する
ルールが破られても、それは「改善が必要」なサインです。
話し合いを諦めないことが、解決への道を開きます。
デジタル機器との付き合い方に、これといった正解はありません。
親子でルールを何度も話し合い、ルールを守らせる。ではなく、ルールを使って子どもが成長できる。そんな関わりを家庭で持っていただくことが大切になります。
実は、mamagirl さんでもスマホとの付き合い方についてインタビューをしていただきました。ルール作りのコツや具体的な関わり方など、詳しくは下記から記事を読んでくださいね。
これからやってくる「夏休み」
長期休みを無法地帯にしないためにも今から備えは必須ですよ!!